足腰大丈夫な内に、出来る限り不要雑物整理をしようと決心してから久しいが、正直あまり捗っていない。書棚や天袋、押入れ等に詰め込まれていた古い書籍や辞書、百科事典等の類も、ここ数年間で大胆に整理処分してきたつもりだが、中には、「これ、面白そう?」等と目に止まり、残してしまったものも結構有る。その中のひとつに、多分、長男か次男かが、学生時代に使っていたものに違いない、小町谷照彦著 文英堂の「小倉百人一首」(解説本・参考書)が有る。パラパラとページを捲ってみたところ、なかなか詳しく、分かりやすく、決して、「今更 向学心?」なーんてものではなく、子供の頃、作者や歌意も分からないまま、「けふ、けふ、けふ・・」「なほ、なほ、なほ・・・」等と、正月になると必ず家族でやっていた「百人一首かるた取り」を思い出して懐かしくなってしまったからで、今更になって、「へー!、そういう歌だったのか・・」、目から鱗・・になっているところだ。
「小倉百人一首」は、奈良時代から鎌倉時代初期までの百人の歌人の歌を、藤原定家の美意識により選び抜かれた秀歌であるが、時代が変わっても、日本人の心情が呼び起こされるような気がしてくる。
ブログネタに?、頭の体操に?、いいかも知れない等と思い込んでしまい、2~3年前、「春」、「夏」、「秋」、「冬」、季節を詠んだ歌を取り上げて、ブログ・カテゴリー「懐かしい小倉百人一首」に書き留めたが、続いて、最も数の多い、「恋」を詠んだ歌を取り上げて、順不同、ボツボツ、書き留めてみることにしている。
しばらく中断していたが、秋も深まりつつある季節、再開することにした。
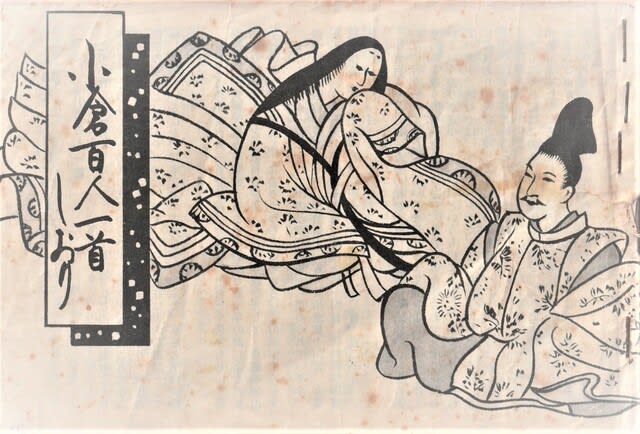
百人一首で「恋」を詠んだ歌 その43
あはれとも いふべき人は 思ほえで
身のいたづらに なりぬべきかな
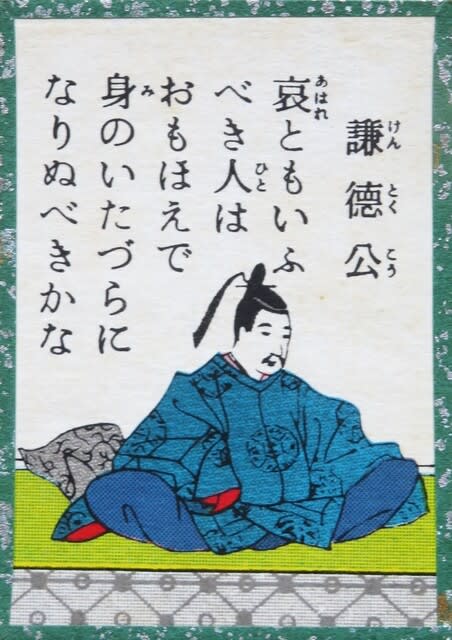
出典
拾遺集(巻十伍)
歌番号
45
作者
謙徳公
歌意
冷たくなったあなたへの恋の悲しさで沈んでいる私を
ああ、可愛そうだ、あわれだと言ってくれる人は、
あなたの他に誰も思い浮かばないので、
私は、きっと、このまま、むなしく死んでしまうだろうなあ。
注釈
「あはれともいふべき」の「あはれ」は、
「ああ、かわいそうに」と訳す感動詞。
「べき」は、「はずの」と訳す当然の助動詞、
または、「そうな」と訳す推量の助動詞。
「思ほえで」の「思ほえ」は、「思ほゆ」の未然形。
自然に思いつくという自発の意味を持つ。
「身のいたづらに」の「身」は、作者自身のことで、
「いたづらに」は、「むなしく」「無駄に」と訳す。
「なりぬべきかな」の「なりぬべき」は、
「きっと、◯◯してしまうだろう」の意。
「かな」は、詠嘆。
「身のいたづらに なりぬべきかな」は、
恋に悩んで死ぬことを意味する時に使われる表現。
「拾遺集」には、
「恋の相手が冷たくなって逢ってくれないので」という
詞書(ことばがき)がついている。
男性の歌としては弱々しく、女々しく感じられる歌だが、
平安時代の男性としては、
恋する人をあくまでも恋い慕うことが真実であり、
このような心情は当然のものであったらしい。
死を思うほど、せつなくやるせない恋の嘆きを表現した作品である。
謙徳公(けんとくこう)
藤原伊尹(ふじわらのこれただ)の諡号(おくりな)
(「諡号」とは、死後、その徳を讃えて送られる呼び名のこと)
摂政太政大臣にまでなり、「一条摂政」とも呼ばれた。
和歌所の別当となり、「梨壷の五人」の主宰者としても知られている。
家集に「一条摂政御集」が有る。
右大臣藤原師輔(ふじわらのもろすけ)の子。
貞信公藤原忠平(ふじわらのただひら)の孫。
藤原義孝(ふじわらのよしたか)の父。
妹の安子(あんし)は、第63代天皇冷泉天皇の母。
娘の懐子(かいし)は、第65代天皇花山天皇の母。
参照・引用
小町谷照彦著「小倉百人一首」(文英堂)
(つづく)